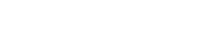青葉区にあるバス停「大場子の神」の名前の由来は?
![]() ココがキニナル!
ココがキニナル!
青葉区に「大場子の神」というバス停があります。なかなかインパクトがあると思いますが、何故このような名称になったのか少しキニナリます。(takedaiwaさんのキニナル)
はまれぽ調査結果!
バス停のある地域の字名から取られたようだ。字名の由来はハッキリしないが、子の神様に関するなにかがあった可能性がある
ライター:田中 大輔
はまれぽでは、これまでもいろいろな変わった名前のバス停について調べてきた。
ただ、これがなかなか難しい。町名や駅名に比べて数が多く、より地域密着しているものだからか、バス会社にも記録が残っていないケースが多いのだ。
今回のテーマは、東急バスの停留所「大場子の神」。
東急田園都市線のあざみ野駅から出る“あ72系統”のみが通るバス停だ。
さて、今回はその名の由来にたどり着けるだろうか。
意外と難読?
まず、このバス停の読み方。
知らないと“おおばこのかみ”と読んでしまいそうだが、正解は“おおばねのかみ”。干支の一番最初、ネズミを指す“ね(子)”の読み方だ。

子、丑、寅、卯・・・の“ね”だ
言葉の節としては、“大場”と“子の神”に分けることができる。
バス停がある辺りは大場町という町だから、“大場”の部分は理解するのも簡単。このバス停の前に「大場坂上」、「大場中央」と通ることからもそれは推測可能だ。

お店が並んでいる。カメラの背後にコンビニと郵便局が
バス停の周辺にはお店や病院、郵便局があってそれなりのにぎわい。
それ以外は住宅街になっていて、比較的新しい一軒家が目立つ。それもそのはずで、この辺りは東急によって開発された新興住宅街なのだ。
子の神様って?
まずは調査の取っ掛かりに、“子の神”について勉強してみよう。
今回は、神社本庁に問い合わせて子の神について教えてもらった。
“子の神”とは日本書紀や古事記などには登場しない神様で、民間信仰の強い神様だそうだ。
出雲大社の分霊とされ、御祭神も出雲大社と同じ大国主命(おおくにぬしのみこと。別名である大巳貴命[おおなむちのみこと]などとしている神社も)。

読んで字のごとく神様の名前?
また、ネズミ(=子)は大国主の使いとされていることや、大国が大黒と読み変えられることに端を発する大国主と大黒点の習合もあり、十干十二支(じっかんじゅうにし。六十干支とも。甲、乙、丙で始まる十干と、子、丑、寅で始まる十二支を組み合わせたもの。古くから年や日に割り振られてきた。戊辰戦争の戊辰もそのひとつで、戦争の始まった年を示している。辛亥革命なども同様)の一番始めである甲子(きのえね)の日を大黒天を祀る日とする信仰が生まれたのだそうだ。 (参考:日本神祇由来事典、柏書房刊)
子の神様に関係する神社は、神奈川神社庁のサイトで調べた限り、市内には少なくとも6社はあるようだ。
つまりは、バス停のあるあの辺りに子の神社があるか過去にあったかしたことから付けられた名前なのでは、という推測が成り立つわけである。
不思議だとは思うけど・・・
再び現地に舞台を移す前に、大元の東急バスに電話取材を試みた。
バス停自体は1997(平成9)年7月に設置されたもので、多摩田園都市の開発の一環で作られたのだそうだ。
しかし肝心の由来については、「明確な由来は分かりません。地域でそう呼ばれていたから付けられた名前だとは思いますが・・・」とのこと。

やはりどこのバス会社でも記録が残っていないケースが多いようだ
バス会社には記録が残っていなかったが、1997(平成9)年の時点でその呼び方が残っていたのなら現地取材でなにか分かるかもしれない。
バス停周辺で、子の神社のことを踏まえつつ地元の人に話を聞いてみた。
ところが、一筋縄にはいかないのがバス停。
話を聞けども「地の人ではないんでねぇ」という答えが異口同音に返ってくる。

きれいに区分けされた住宅が並ぶ。地の人に出会うことはできなかった
そう、この辺りは新興住宅街。
昔から住んでいるという人が少なく、皆さん「不思議な名前のバス停だと思っていた」と言いつつも、その由来については知らないのだそうだ。