野毛の伝統といわれる流し芸ってナニ?
![]() ココがキニナル!
ココがキニナル!
今年、3年ぶりに野毛で再開された柳通り流し芸ってどんな催しなの?(はま爺さんからのキニナル)
はまれぽ調査結果!
三味線や和楽器の音色に合わせて唄あり、踊りあり、歓談あり。演芸を身近に感じさせる、下町情緒たっぷりのイベントだった。
ライター:木全 圭
まるで70軒の店がセッションしているかのよう
その他の店も同様の盛り上がり様だった。そんな活気に誘われて、ふらり立ち寄る後発の飲み客も少なくない。柳通りの至る所から三味線や和楽器の音色、そして客の拍手喝采が届いてくるので、「何事か?」と他の通りから遠征して来るのだ。
卓に着いて演奏を披露するのは、野毛山節保存会で会長を務める片山浪(なみ)さん。
この一体感は、流し芸独特のものであろう
アフロビートと日本の古典音楽の融合を目指すバンド「ZIPANG」のリーダー、岩間哲也さんは、
ティンゴさんのギター&ブルースハープとセッションを決め、注目を浴びていた
津軽三味線・藤田流二代目藤田淳哉を襲名した湯浅大吾さんを、
ノスタルジックな雰囲気漂うバーで発見。違和感がない!
ところで、流し芸はいつから野毛に根付いたのだろう? 山田会長いわく、「それについては新内節相模派家元の富士松延治太夫(ふじまつえんじだゆう)さんが詳しいです」とのこと。延治太夫さんはこの日の出演芸人の一人なので、後日、彼の稽古場へと足を運ぶことにした。
伝統の文化だからこそ廃れさせたくない
「私が野毛の町内会に提案して、平成元年(1989年)、流し芸が始まったんです。流し芸は店に見物人が集まるのだから、町を潤すには最良の手段でしょう」
日ノ出町駅の側に構えられた稽古場で、延治太夫さんはそう教えてくれた。つまり、彼こそが柳通り流し芸の発起人なのだ。当時は野毛の町全体で流し芸が行われていたそうで、見物人が大勢押し掛け、「野毛一帯の焼き鳥が売り切れてしまった」なんていう珍事もあったそう。
客は楽しく飲食できて、店は売上げが上がり、芸人は投げ銭を
いただくことができる。流し芸は、経済効果を向上させる優れた文化!?
吉原かむりに着流し姿で新内流しを披露する富士松延治太夫さん
普段も、馴染みの居酒屋や料亭から度々お呼びがかかるそうだ
「カラオケが流行る以前は、流しのギター弾きや演歌師が、どこの街にもいたもんです。野毛は、当時の雰囲気を残した町だから、流し芸の文化も廃らしてはいけないと思うんです」
1944(昭和19)年に横浜で生まれ、18歳で野毛に移り住み、25歳で新内節に入門したという富士松延治太夫さん(本名:飯田喜弘さん)。
40歳で脱サラし、この道一本でやっていくと決意したのは、「会社は一人が欠けても代えがいるけど、伝統芸能の世界は一人が欠けたら大きな損失になる」という理由から。
同じように、野毛の伝統も絶やさず、伝えていかなければいけないという使命感が、きっと彼にはあったのだろう。
「流し芸のルーツといわれる新内節。その富士松の一門でプロとしてやっているのは、横浜では私だけ。全国でも20人弱です。だからこそ、その音色に触れ合える貴重な場として、野毛の町に足を運んでもらいたいですね」
幅広い年齢層の入門者が増えてほしいというのが、延治太夫さんの願い
新内節に関しては、延治太夫さんの公式サイトに詳しく説明があるので、そちらを参照してほしい。三味線教室や公演会の案内なども掲載されている。
とにもかくにも、40年間、伝統芸能の世界に携わってきた人の言葉には、やはり重みがある。思わず背筋を伸ばして聞き入ってしまったほどだ。この数年で、 横浜の再開発は急ピッチで進み、都市としての利便性は飛躍的に向上した。けれど、確実に失われていったものも多くあることを、延治太夫さんの言葉は暗に指 し示しているように思えてならない。
そう、人々が笑顔で暮らしていくには、何もかもが時流の最先端である必要などないのである。取材の折に立ち寄った『もみぢ菓子司舗』のように、アナログな 環境だからこそ得られる温もりというものもある。現に、芸人たちを取り囲む見物人たちからは、その場に居合わせた幸運を共有する連帯感みたいなものが感じ られた。
この人情味溢れる文化が廃れないよう、いや、全国に広がるように、次回開催の際にはみなさんもぜひ足を運んでいただきたい。
―終わり―
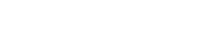










 面白かった
面白かった 面白くなかった
面白くなかった コメントする
コメントする













