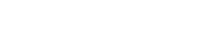鶴見のめがね橋は目が一つしかないけどなぜめがね橋なの?
![]() ココがキニナル!
ココがキニナル!
鶴見の国道1号線にかかる響橋は「めがね橋」の愛称で親しまれているのですが、【目】が一つしかなくメガネにならないのですが・・・何故めがね橋とよばれるのでしょうか?(あんずパパさんのキニナル)
はまれぽ調査結果!
役所や地元にも、聞いてみたが理由は分からなかった。ただ、横浜には本当のめがね橋があることが判明した!
ライター:ワカバヤシヒロアキ
鶴見のめがね橋とは?
鶴見区東寺尾北台―北寺尾に国道と市道が交差するポイントがある。
下を通るのは国道1号線。上には陸橋が架かり、市道85号鶴見獅子ヶ谷通りが通っている。
その陸橋部分こそが、響橋(ひびきばし)、通称「めがね橋」なのだ。
響橋は、1941(昭和16)年に建築され、横浜市認定歴史的建造物や、かながわの橋100選にも選出されている橋梁である。

国道1号線から見るめがね橋
そんな歴史深く、由緒正しき橋なのだが一点気になることがある。
どう見てもアーチは1つしかなく、「めがね橋」と称するには少々無理があるように思う。
日本全国に見られる「めがね橋」はどのような構造になっているのか?いくつか例を挙げてみる。

長崎めがね橋、見事に2本のアーチがめがねを表現している

群馬にある碓氷第三橋梁もめがね橋と呼ばれている

岩手県遠野市にある宮守川橋梁は、5つのアーチが並んでいる
いずれも、日本有数のめがね橋である。2つ以上のアーチが並んでいることがめがね橋の条件になっているようだ。
大辞林には、
『めがね‐ばし【眼‐鏡橋】 石造りで半円形が二つ並んだ形の橋』
と記されている。鶴見区の響橋にある1つのアーチは、果たしてめがね橋と名乗っても良いのだろうか?

めがね橋と言えるのだろうか?
近隣の人の反応は?
ちょっと無理のある、片レンズの「めがね橋」。地元の人はどのように思っているのだろうか?
まず、めがね橋の下にあるバス停にいた女性に話しを聞いてみた。

めがね橋の下にあるバス停にいた女性
―めがね橋っていう呼び方は御存知ですか?
「ええ、知っています。きれいな形をしていてね」
―めがねだと、普通は2つのアーチがありますよね?
「ああ、そうですね。でも、ここは1つだけみたいですね」
続いて、『めがね橋新聞』を発行している、寺尾地域ケアプラザのスタッフの女性にも話を伺った。
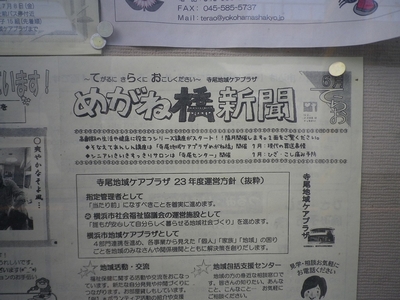
PDF版もあるようだ
―新聞のめがね橋というのは響橋のことですか?
「そうです。めがね橋という愛称ですので」
―でも、1つしかアーチが無いですよね?
「そうですね、でもここはめがね橋と言うみたいです。確かにちょっと不思議ですね」
歩きながら聞き込みをしていると、めがね橋のすぐ近くに、老舗のメガネ屋さんを発見。
これは偶然なのだろうか? 何か新事実が分かるかもしれないと思い話を聞いた。

めがね橋の上にメガネ屋さんが
―ここのメガネ屋さんはめがね橋と関係があるのですか?
「何も無いよ」
―そうですか。アーチが1つしか無いのにメガネ橋というのはおかしいですよね?
「そうだね。でも、何故だかはわかんない」
最初は少しぶっきらぼうな店主さんであったが、少し話をすると「元々山をくり抜いて国道1号を通し、その上に市道を通すために架けられたのが響橋」と、橋が出来た経緯を教えてくれた。
また、店主さん曰く、橋の上に柵が設けられているのは飛び降り自殺の防止なのだそう。

めがね橋の上側、確かに柵はすごく高い
近隣の人には、めがね橋という愛称が十分に認知されていた。ただ、アーチが1つしかない事に関しては、疑問に思いつつも、理由はよくわかっていないようであった。
これはもう横浜市の担当者に聞くしかない。
横浜市道路局建設部橋梁課に行って話を聞いた。